
こんにちは。
今回は少し歴史をさかのぼって、
「日本に英語が入ってきたころ、どんなふうに学ばれていたのか?」
というお話をしてみたいと思います。
特に、福沢諭吉のように
幕末から明治初期にかけて英語を身につけた人々の学び方は、
現代にも通じるヒントがたくさんあります。
📘 英語は「会話」より「翻訳」のためだった
幕末当時、英語は“話すための道具”ではなく、
- 外国の書物を読むため
- 外交文書を理解するため
という目的で学ばれていました。
だから、まず必要だったのは「読む力」。
とにかく洋書を手に入れて、
辞書と格闘しながら、
一文ずつ読み、訳して覚える
という作業が中心でした。
✍️ 「写経」のように英語を学ぶ
教材やテキストが整っていなかった時代、
英語学習はまるで写経のようなものでした。
- 洋書を書き写す
- 単語を辞書で調べる
- その意味を考えて訳す
福沢諭吉も、最初はオランダ語を学んでいましたが、
横浜で英語の看板を見て「これからは英語だ」と直感し、
独学で英語へと切り替えたと言われています。
👥 会話力は「現場」で身につけた
当時、ネイティブスピーカーと会話できる環境は
限られていました。
それでも、福沢諭吉は幕府の使節団として海外を訪れたことで、
現地で生の英語に触れる機会を得て、
実践的な英会話力を習得しました。
また、開港地の横浜や長崎などでは、
通訳や貿易の現場で
外国人とやりとりする中で
英語を“体で覚える”人も多くいたそうです。
🔁 彼らの基本は「くり返し」だった
CDも動画もアプリもない時代。彼らができたのは、
- 書く
- 読む
- 声に出す
この3つを、何度も何度も繰り返すことだけ。
だからこそ、
自分の体と感覚を使って英語をしみ込ませるしかなかったのです。
✅ 今の私たちにも通じる学びの本質
当時と今とでは環境はまったく違いますが、
「意味のわからないものを、自分で理解しようとする」
「わかるまで繰り返す」
という本質的な学びの姿勢は、
今も変わりません。
だからこそ、便利なツールに頼るだけでなく、
英語を“くり返して、使って、
自分のものにする”姿勢が やはり大切なのです。
次回予告:
次回は、こうした歴史の学びをふまえて、
「じゃあ、いま本当に“話せるようになる”学びって、どんなものなのか?」
をまとめていきます。
学び方が変われば、英語はきっともっと身近になります。






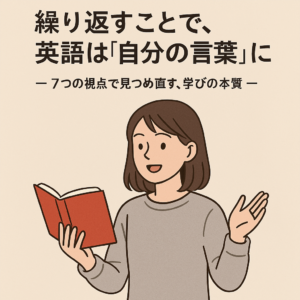
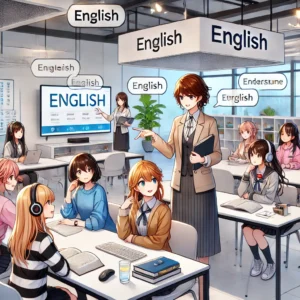
コメント