
第2回|繰り返し学習は、ただの作業じゃない
こんにちは。
前回は、英語を覚えるまでにかかる回数が人によって違うこと、
そして「繰り返し」が学習の本質であるというお話をしました。
今回はその「繰り返す」という行為について、
もう少し掘り下げてみたいと思います。
🔁 くり返すことで、脳は“気づき”を得ている
同じ英語表現を何度も聞くと、
ただの作業に見えるかもしれません。
でも実は、そのくり返しの中で、
脳は少しずつ新しい情報を取り込んでいます。
- 2回目で「あれ?この音のつながり、前と違って聞こえるな」
- 3回目で「この単語、さっきのと似てるけど意味が違う」
- 4回目で「もしかしてこの“the”って弱く発音してる?」
そうやって、
同じことを繰り返す中で“違い”に気づく。
これこそが、学習の正体なんです。
👂 くり返しが「聞こえなかった音」を聞かせてくれる
初めて英語を聞いたとき、
「まるで早口言葉」のように感じることってありますよね?
それは、脳がまだ音の区切りやリズムをつかめていないからです。
でも、何度も同じ音を聞くうちに、
「あ、ここで区切れてる」
「ここで強く読んでる」
といったリズムのパターンが見えてくるようになります。
くり返すことで、
音の“モヤモヤ”が“輪郭”になっていく。
だからこそ、聞き取れるようになるんです。
📚 作業に見えて、実は「蓄積」されている
よく「繰り返すだけなんて、ただの作業じゃないか」と言われます。
でも、脳は何度も同じ情報に触れることで、
少しずつ処理がスムーズになり、
自然と“身についた感覚”が育ちます。
しかもこの感覚は、
あるとき突然
「あれ?わかるようになってる!」
という形で現れます。
そのときには、もう意識的に考えなくても、
英語のフレーズが口から出るようになっているかもしれません。
✅ だから「ただの繰り返し」を恐れないで
繰り返すことに意味があるの?
また同じところで止まってるの?
そんなふうに思わずに、
むしろ同じことを何度もできるってすごいことなんだと
思ってほしいのです。
英語は「慣れ」がすべて。
繰り返しが、
その“慣れ”をつくってくれます。
次回予告:
次回は、「なぜ多くの子どもたちが英語に自信を失ってしまうのか?」
という問題に触れてみたいと思います。
文法中心の教育の中で、どんなつまずきが起きているのか。
そこから抜け出すヒントもお伝えします。






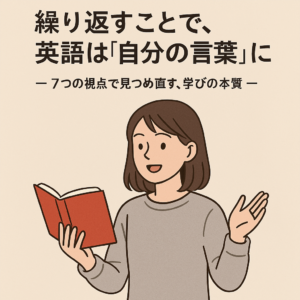
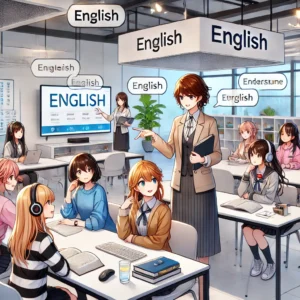
コメント